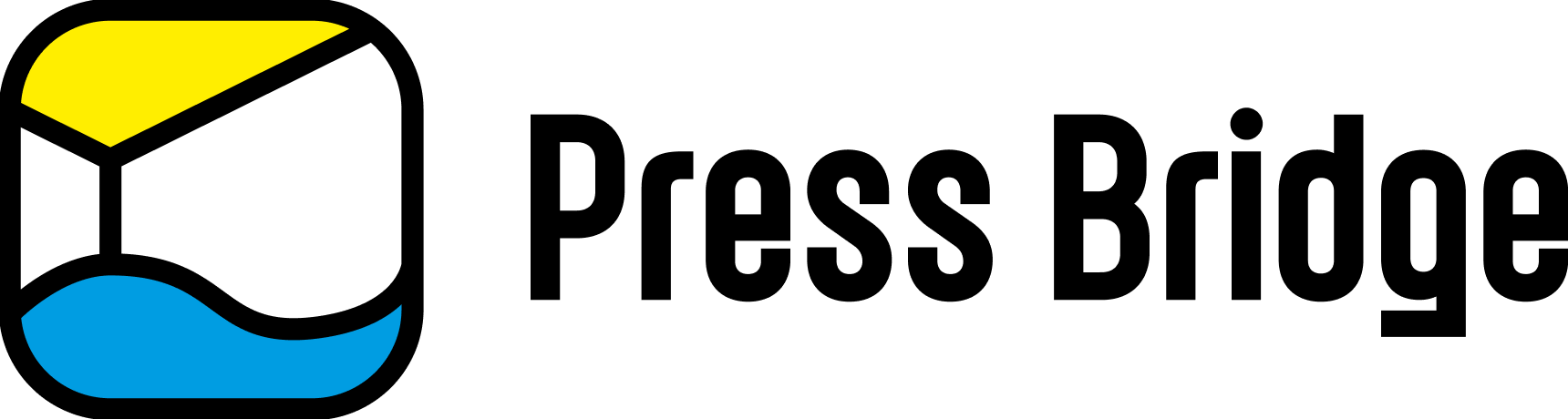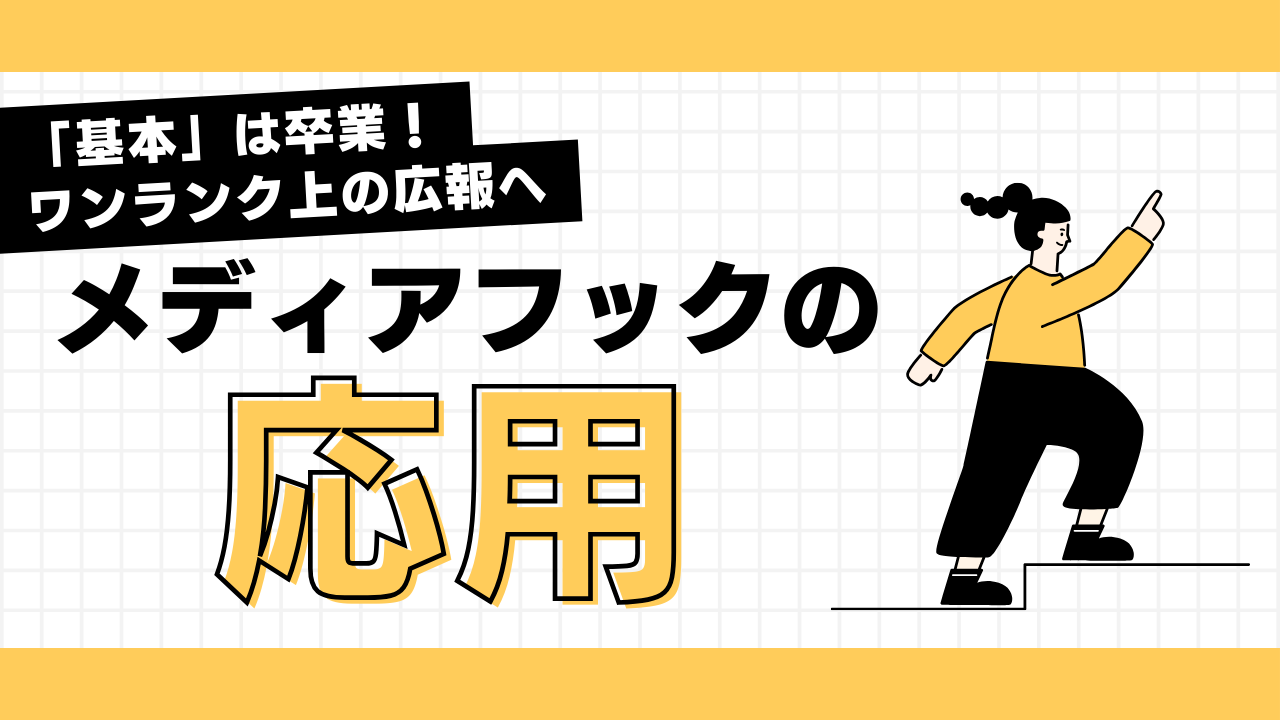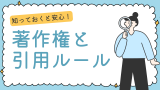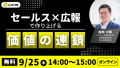広報担当者として数年の経験を積むと、「プレスリリースを出せばメディアに載る」という単純な世界ではないことに気づきます。基礎的な広報活動は一通りこなせるけれど、思ったほど取材が来ない…。そんな壁に直面するのが中堅広報です。
ここでカギになるのが「メディアフック」。記者の心をつかむ切り口を仕掛けることで、自社の話題を“ニュース化”する技術です。初級編では「8つのメディアフックの要素」をご紹介しました。
しかし、記者の目に留まり、取材へとつながるプレスリリースには、その一歩先の「応用テクニック」が隠されています。
この記事では、記者が「これ、面白いね」「ぜひ取材させてください」と思わず言われるような、ワンランク上のメディアフック活用術を、具体的な事例を交えながら徹底解説します。広報初心者の方もぜひご覧ください。
基礎のおさらいと陥りがちな落とし穴
まずは、メディアフックの基本を簡単におさらいしましょう。
▼【初級編】記者の関心を引き寄せるメディアフックとは?
初級編の記事でお伝えしたメディアフックの「8つの要素」は、ニュースのタネを見つけるための大切なヒントです。
- 時流/話題/季節性(旬ゴト)
- 社会/公共・公益性(社会ゴト)
- 地域性(地域ゴト)
- 新規性/新奇性(独自ゴト)
- 最上級/希少性(一番ゴト)
- 人物/企業名(あやかりゴト)
- 逆説/対立/意外性(へぇゴト)
- 数字/絵(映えゴト)
これらの要素を意識することは、広報活動の第一歩として非常に重要です。しかし、中堅広報が陥りがちな「落とし穴」があります。それは、「要素をただ当てはめるだけ」になってしまうことです。
例えば、「新規性」というフックを使って「新商品リリース」のプレスリリースを出したとします。しかし、同じ時期に競合他社も似たような新商品を多数リリースしている場合、あなたのプレスリリースはその他大勢の中に埋もれてしまいます。
なぜなら、記者は毎日何百通ものプレスリリースに目を通しており、「ただ新しいだけ」の情報にはもう慣れてしまっているからです。
目指すべきは、「要素を単体で使う」のではなく、「複数の要素を掛け合わせ、記者の『知りたい』を刺激する」ことです。記者の思考プロセスを理解し、「この情報は、どのメディアの、どんな記事になるだろうか?」という視点を持つことが、取材獲得への鍵となります。
取材したくなる「記者目線」を掴む、逆算思考のメディアフック戦略
では、具体的にどうすれば記者の関心を惹きつけられるのでしょうか?その答えは、「逆算思考」にあります。
記者は、プレスリリースを読んで、その情報を記事にできるかどうか、読者が興味を持つかどうかを瞬時に判断します。彼らの頭の中では、常にこのような思考が巡っています。
- 「この情報は、誰に伝えたい情報か?」(ターゲット読者)
- 「どんな切り口で書けば、読者は面白いと感じるか?」(記事の企画)
- 「どのメディアの、どのコーナーで掲載するのが最適か?」(掲載枠)
この記者の思考プロセスを先回りして、あなたのプレスリリースに反映させるのが「逆算思考」のメディアフック戦略です。
【実践ステップ】
- ターゲットメディアを絞る
- まずは、自社の情報を掲載してほしいメディア(新聞、テレビ、専門誌、ウェブメディアなど)を具体的にリストアップします。
- メディアの「読者像」を想像する
- そのメディアの読者はどんな人たちでしょうか?年齢層、職業、興味関心、ライフスタイルなどをできるだけ具体的に想像します。
- 「読者」に響くフックを逆算する
- 想像した読者像が「へぇ!」と思うような、あるいは「自分ごと」として捉えてもらえるようなメディアフックを考えます。
【具体例】
例えば、あなたの会社が「AIを活用した食品ロス削減サービス」を開発したとします。
- 「新規性」だけでは不十分:「当社はAIを活用した新しい食品ロス削減サービスを開発しました」というだけでは、記者は「ふーん」で終わってしまいます。
- 逆算思考でフックを再構築:
- ターゲットメディア: ビジネス系新聞
- 読者像: 企業の経営者、ビジネスパーソン、投資家
- 逆算フック: 彼らが関心を持つのは「ビジネスとしての可能性」や「持続可能な社会への貢献」です。
- 完成したフック: 「国内の食品ロス市場規模は〇〇兆円に達する中、AIで廃棄コストを〇〇%削減。大手スーパーとの実証実験で、フードテックの新たなビジネスモデルを確立」
この例では、「数字(映えゴト)」と「社会性(社会ゴト)」、「新規性(新規ゴト)」を組み合わせ、さらに「経済」という切り口を加えることで、記者が記事化しやすい「明確なニュース価値」を生み出しています。
単発で終わらせない!複数のメディアフックを組み合わせる「ストーリーテリング」
一度取材された終わり、ではもったいないですよね。中堅広報は、単発の取材にとどめず、「この企業は今後も注目すべきだ」と感じてもらえるよう意識する必要があります。
そのために有効なのが、複数のメディアフックを組み合わせて一つの「ストーリー」を語ることです。
【具体例】
例えば、あなたの会社が新しい「環境配慮型素材」を開発したとしましょう。
- フック①:新規性(新規ゴト)
- 「世界初!植物由来のプラスチック代替素材を開発」
- フック②:社会性(社会ゴト)
- 「プラスチック問題の解決に貢献する新素材」
- フック③:地域性(地域ゴト)
- 「素材開発のきっかけは、地域のお祭りでのゴミ問題」
- フック④:人物/企業名(あやかりゴト)
- 「この技術は、〇〇大学の権威ある教授との共同研究から生まれた」
- フック⑤:数字/絵(映えゴト)
- 「従来のプラスチックと比較して、CO2排出量を〇〇%削減」
これらのフックを、プレスリリースの中で線でつなげてみましょう。
「当社は、プラスチック問題という社会課題(社会ゴト)の解決を目指し、〇〇大学の〇〇教授と共同で(あやかりゴト)、世界初(独自ゴト)となる植物由来の新素材を開発しました。この素材は、従来のプラスチックに比べてCO2排出量を〇〇%削減できる(映えゴト)だけでなく、地域のお祭りでのゴミ問題(地域ゴト)を解決したいという想いから生まれたものです。」
単に「新素材を開発しました」という情報よりも、背景にある「想い」「つながり」「社会的な意義」が加わることで、プレスリリース自体が「物語」になります。
記者は、この「物語」から、さらに多くの記事の種を見つけ出すことができます。例えば、「開発者のインタビュー」「大学教授の専門的見解」「地域のお祭りでの導入事例」など、多角的な取材に発展する可能性が生まれるのです。
データを武器に!最新トレンドと数字で「説得力」の増強
説得力のあるメディアフックを作る上で、「データ」は最強の武器になります。記者は、客観的な事実や数字に基づいた情報を求めています。
最新の市場動向や公的機関の調査データを引用することで、自社の情報が「社会全体にとって重要な情報」であることをアピールできます。
【具体例】
例えば、あなたが「高齢者向け見守りサービス」の広報担当者だとします。
- フック①:「新機能『AIが異常な行動パターン検知』を搭載した高齢者見守りサービスをリリース」
- フック②:「内閣府の令和5年版高齢社会白書によると、65歳以上の高齢者人口は〇〇人に達し、総人口に占める割合は過去最高に」
- フック③:「当社の実証実験では、この新機能によって孤独死のリスクを〇〇%低減できることが分かりました」
この場合、フック①だけでは単なる新商品情報ですが、フック②の公的なデータを引用することで、「今、なぜこのサービスが必要なのか」という社会的な背景を説得力をもって伝えることができます。さらにフック③で具体的な効果を示す数字を提示することで、サービスの有用性を明確に示せます。
引用する際のポイント
- 信頼性の高い情報源を選ぶ: 公的機関(省庁、研究機関など)、信頼できる調査会社、専門家の論文などを引用しましょう。
- 出典を明記する: 「〇〇(機関名)の調査によると…」と出典を明記することで、情報の信頼性が向上します。
- 最新のデータを使う: 古いデータではなく、できるだけ最新のデータを引用することで、情報の鮮度を保ちます。
▼あわせて読みたい
思わず読みたくなる!「見出し」と「リード文」の磨き方
どんなに素晴らしいメディアフックを練り上げても、記者がプレスリリースを読んでくれなければ意味がありません。プレスリリースの顔である「見出し」と「リード文」こそ、フックを最大限に際立たせるための重要なパーツです。
【見出しのテクニック】
見出しは、フックを凝縮して伝える役割を担います。
- 数字やキーワードを盛り込む 例:「食品ロス〇〇%削減!AIで実現するサステナブルな未来」
- 記者が記事にしやすいフレーズを使う 例:「〇〇問題解決へ。スタートアップが開発した新サービスが、業界に一石を投じる」
- 「意外性」を強調する 例:「冬なのにアイスが売れる理由。老舗メーカーの『逆説的』新戦略」
【リード文のテクニック】
リード文は、見出しで引きつけた記者の興味をさらに深め、「このプレスリリースには、続きを読ませる価値がある」と確信させる役割があります。
- 「結論ファースト」を徹底する 「○○は、〇〇という社会課題を解決するため、〇〇を開発しました」のように、最も伝えたい結論を最初に述べます。
- 「なぜ今、この情報が重要なのか」を明確にする 「近年、○○市場は急成長を遂げており、〇〇という課題が顕在化しています。こうした背景から…」のように、社会的背景やトレンドに触れることで、情報の緊急性や重要性を示します。
- フックをリード文にも散りばめる 見出しで使ったフックを、冒頭文でも具体的な言葉で補足します。
見出しとリード文は、記者が「このリリースは、自分の担当分野で使えるニュースだ」と判断するための最初の関門です。ここでフックを明確に提示することで、読んでもらえる確率が格段に上がります。
まとめ
これらの応用テクニックは、一朝一夕で身につくものではありません。しかし、日々の広報活動の中で意識し、実践を繰り返すことで、あなたのスキルは確実に向上します。
記者は、「自社の都合」ではなく「読者のためになる情報」を求めています。この本質を理解し、あなたの会社のユニークな情報を、社会の動きや人々の関心事と結びつけることができれば、必ず記者の心を動かすことができるはずです。
今日からぜひ、「フックを武器にする広報」へとステップアップしていきましょう!