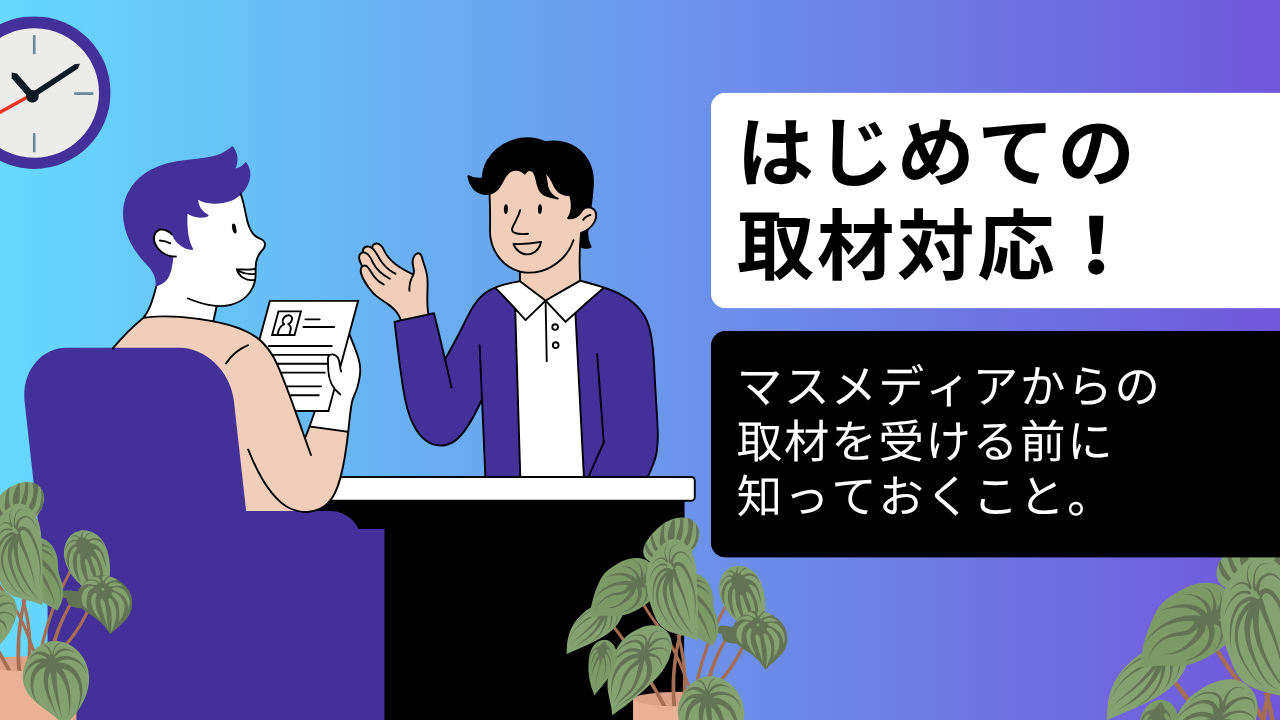基本的な心構え
- 記者・編集者と企業は、良い記事をつくる「協力関係」であることが大切です。
- 対立関係ではなく、相手も読者にとって有益な記事を目指している点を理解しましょう。
原稿確認はできません
なぜできないのか?
- メディアには 「編集権」 という権利があり、中立・公正な報道のために 編集内容の事前確認はできません。
NGな対応例
- 「事前に見せてもらえますか?」といった確認依頼は、編集権の侵害にあたる可能性があり、“圧力”や“信頼欠如”と受け取られるリスク を含んでいます。
- また、広報担当者がNGと伝えているにも関わらず、現場で誰かが再確認するのは広報担当者の信頼を損なってしまいます。
数字などどうしても不安なときは
- 「数字だけ確認できますか?」など、相談するスタンスで、事実確認(ファクトチェック)にとどめる 配慮が望ましいです。
- コラムなど、代表の起業ストーリーや人生の深掘りインタビューなどでは、内容確認できるケースもありますが、これもファクトチェックが目的です。
記者・編集部の立場とリスク
- 記者が事前確認に応じることで、 懲戒処分等の対象になることもある ため、慎重な対応が求められます。
補足:編集権とは?
編集権とは、報道機関が記事の編集方針を決定し、報道の真実や評論の公正、公表方法の適正を維持するための権能を指します。具体的には、報道機関が自身の判断で記事を書き、編集する独立した権限のことです。 日本新聞協会が1948年に発表した声明で、「新聞の編集方針を決定施行し報道の真実、評論の公正並びに公表方法の適正を維持するなど新聞編集に必要な一切の管理を行う権能」と定義されています。
取材を受けるときのポイント
正直さ
- 嘘をつかない。誠実さをもって対応し、読者・視聴者や社会を欺こうとしないこと。
わかりやすさ
- カタカナや専門用語の多用は避けて、簡潔な言葉で説明を。
- 資料を用意するなど、伝わりやすさへの工夫を。
曖昧なことを正しい情報のように伝えない
- 曖昧な数字や未確定な事実は避けましょう。
- 追って答えられる場合は、その旨を伝えて、改めて正確な情報を共有しましょう。
【メディア別】具体的な注意点
ニュースメディアの場合
- タイトルや見出しには 「数字的インパクト」や「新奇性」など が求められます。
- 取材終盤の気軽なアイスブレイクでの発言が見出しになることもある ので要注意!
発言例:「新サービスのプロジェクトは動き始めてますよ〜」→ 記事タイトル:「A社、来春新サービス発売予定」
テレビ取材の場合
- 視聴者層が広範囲にわたるため、特に、業界用語やビジネス用語、横文字を避けましょう。
- (カメラが回っている時)問いへの返答は 繰り返して答える のがベター。
- 記者やレポーターの質問はカットされる場合があるため、使えるコメントをするために「はい・いいえ」などの 単語だけで終わらないように意識。
問い:「このサービスは、EC事業者向けですか?」
NG:「はい、そうです。」 ←単独で使えない
OK:「はい、EC事業者向けのサービスです。」
オフレコについての基本的な考え方
オフレコの原則を理解し、相手との信頼関係を前提に判断を。
重要な情報を「これはオフレコです」と明示するのは基本ですが、相手が必ずしもその扱いに同意しているとは限らず、事前に合意を取ることが前提です。
オフレコ取材は本来、記者と取材対象者の間に築かれる相互信頼の上に成り立つ取材方法であり、事実の背景や深層を伝えるうえで一定の役割を果たしてきました(参考:日本新聞協会編集委員会見解)。
ただし、関係性が浅い記者や、スタンスが把握できていないメディアに対しては、重要度の高い非公開情報は話さないのが鉄則です。
また、オフレコと伝えても、話した内容が表に出てしまうケースもあります。発言内容そのものに慎重を期すことが、広報としての基本姿勢です。