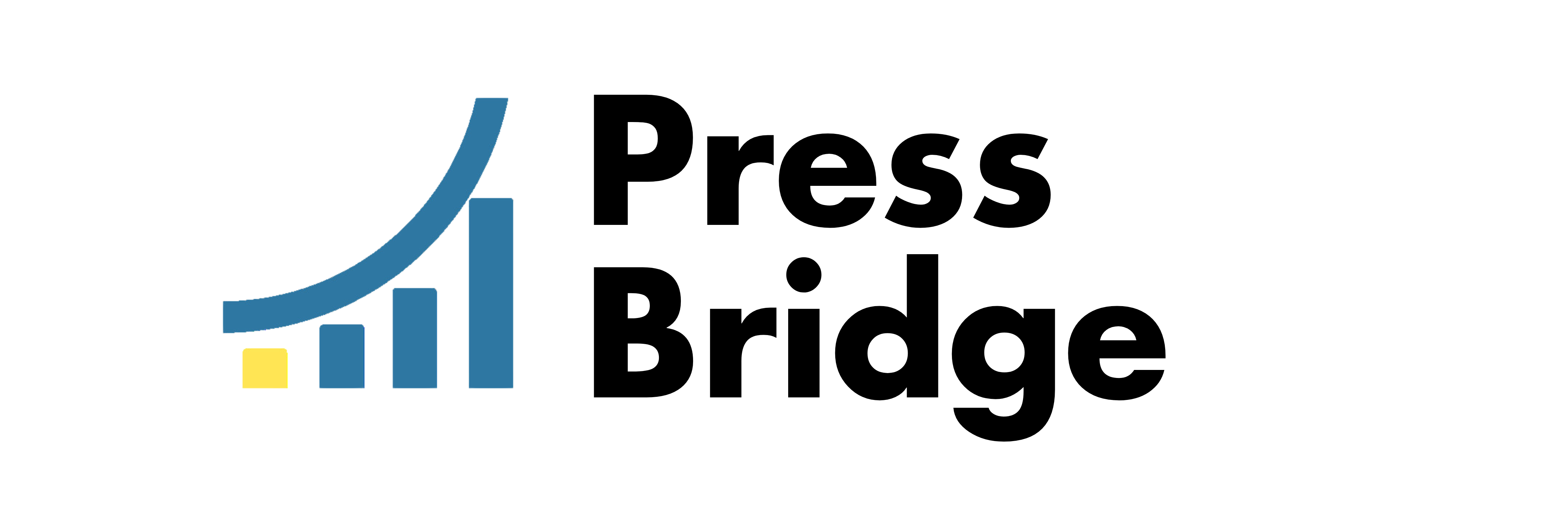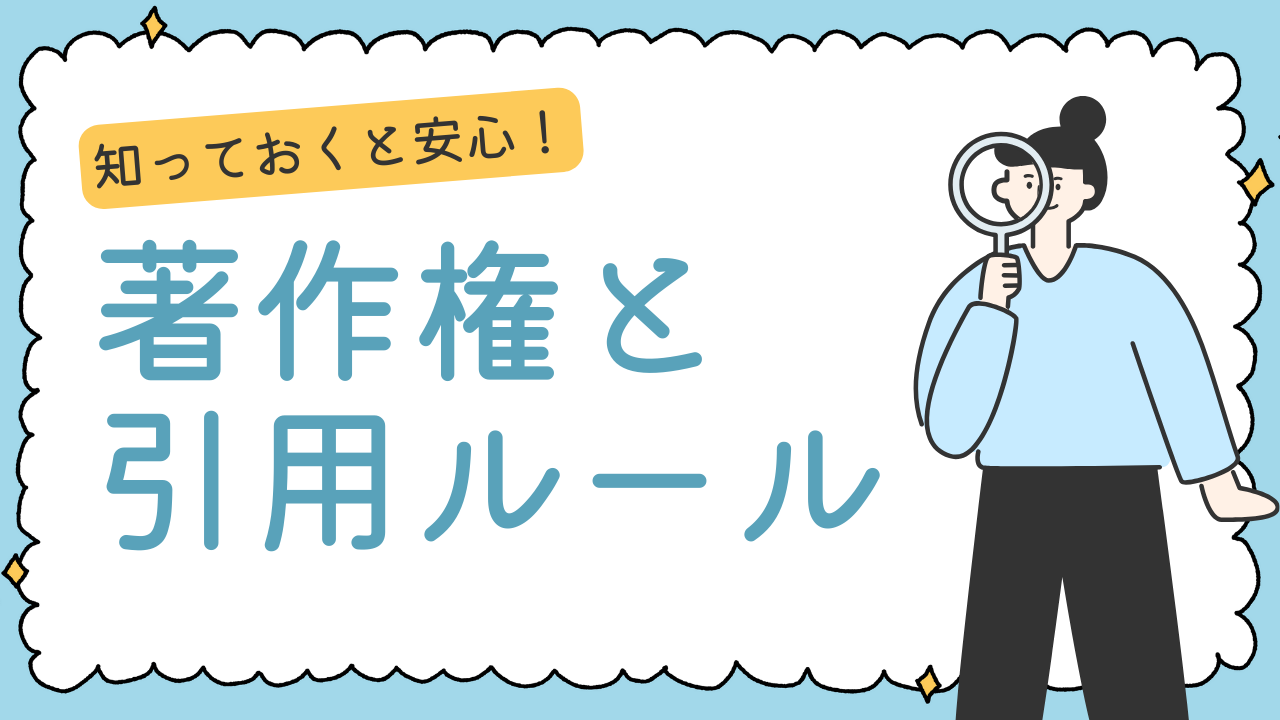広報を担当していると、プレスリリースやSNS投稿、ウェブサイト運用などで他社のコンテンツを参考にする機会が増えます。しかし、「引用のルールがよくわからない」と悩む広報担当者も少なくありません。
著作権の基本を押さえ、正しく引用や素材の利用を行うだけで、炎上リスクや法的トラブルを避けつつ、クリエイティブな広報活動が可能になります。本記事では、広報初心者でもわかるように、著作権の基礎知識から引用ルール、フリー素材の活用法まで、具体例を交えて丁寧に解説します。
「知らなかった」では済まされない著作権リスクから企業と自分を守るために、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも「著作権」って何?広報担当者が押さえるべき3つのポイント
「著作権」と聞くと、なんだか難しそうな法律用語が並んでいて、少し身構えてしまいますよね。でも、実務で必要なポイントは実はとてもシンプルです。まずは基本となる3つのポイントを押さえましょう。
ポイント①:広報活動で扱うほとんどのものが「著作物」
では、具体的にどのようなものが著作権で守られる「著作物」なのでしょうか?著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法第2条第1項第1号)。
広報の現場で扱うもので言えば、以下のようなものが当てはまります。
- 文章:プレスリリース、ブログ記事、調査レポート、書籍・雑誌の記事、他社のウェブサイトの文章など
- 画像:自分で撮影した写真、デザイナーが作成したイラスト、図やグラフ、ロゴマークなど
- その他:プレゼンテーション資料、講演内容、動画コンテンツ、音楽など
逆に、単なる事実やデータ(例:本日の東京の気温、交通情報)、ありふれた表現や短い言葉(例:スローガン、時候の挨拶)は、創作的な表現とは言えず、著作物には該当しないとされています。
ポイント②:著作権は「創った時点」で「自動的」に発生する
これが一番大切なポイントです。小説、音楽、イラスト、そして私たちが日常的に書くブログ記事や撮影する写真など、これらが創作された瞬間に、著作権は自動的に発生します。特許権や商標権のように、役所に申請したり登録したりする必要は一切ありません。これを法律用語で「無方式主義」と言います。
Webサイト上に「無断転載禁止」やコピーライトマーク(©)が書かれていなくても、そこに掲載されている文章や写真には、ほぼ間違いなく著作権が存在する、と考えておくのが正解です。
ポイント③:権利が続く期間は、とっても長い
著作権は永遠に続くわけではありませんが、非常に長い期間保護されます。原則として、著作者の死後70年までです。法人が著作権を持つ映画や写真などの場合は、公表後70年となります(著作権法第51条~第54条)。
つまり、私たちがインターネット上で目にするほとんどのコンテンツは、著作権の保護期間内にあるということです。「昔の作品だから大丈夫だろう」と安易に判断するのは非常に危険です。
このポイント3つを頭に入れておくだけで、「あ、これも誰かの大切な著作物かもしれない」という意識が芽生え、無用なトラブルをぐっと減らすことができます。
これで完璧!堂々と使える「引用」の5つの条件
他人が創作した著作物を無断で利用することは、原則として著作権侵害になります。しかし、それでは新しい情報を発信したり、批評したりすることができなくなってしまいますよね。
そこで法律で認められているのが「引用」というルールです。このルールを守れば、著作権者の許可を得なくても、例外的に他者の著作物を利用することができます。
ここでは、文化庁の考え方を基に、実務で絶対に外せない「5つの引用条件」を分かりやすく解説します。
条件①:引用する必然性があること
まず大前提として、自社のコンテンツを作成する上で「どうしてもその著作物を引用する必要がある」ことが求められます。例えば、他社の調査データを紹介して自社の見解を述べたり、専門家の意見を引いて自社製品の優位性を説明したりする場合などがこれにあたります。単に「文章量を増やしたいから」「デザイン的に寂しいから」といった理由での利用は、引用とは認められません。
条件②:自分の文章と引用部分が明確に区別されていること(明瞭区別性)
読者が一目見て、「どこからどこまでが引用部分か」がはっきりと分かるようにしなければなりません。
例:カギ括弧で囲む、引用部分を太字や斜体にする、blockquoteタグ(HTML)を使ってデザインを変えるなど。
条件③:自分の文章が「主」、引用部分が「従」であること(主従関係)
記事全体のボリュームを見て、自分の文章がメイン(主)で、引用部分はそれを補足するサブ(従)の関係になっている必要があります。質の面でも、引用部分がなくても記事の骨子が成り立つことが重要です。
例:記事の9割が自社の考察で、根拠を示すために1割だけ他社のデータを引用する。
条件④:引用元をきちんと明記すること(出所の明示)
「どこから引用してきたのか」を、読者や元の著作者が分かるように、正確に記載する義務があります。これは著作物と著作者に対する最低限のマナーでもあります。
- 記載すべき情報:
- Webサイトの場合:サイト名、記事タイトル、URL
- 書籍の場合:書名、著者名、出版社名、発行年、該当ページ
条件⑤:引用部分を勝手に変えないこと(同一性保持権の尊重)
引用する文章や画像は、原則として一字一句、一切改変してはいけません。文章の一部を省略する場合は「(中略)」と明記するなど、元の意図を歪めない配慮が必要です。誤字脱字を見つけても、勝手に修正してはいけません。これは著作者が持つ「同一性保持権」という権利を守るためです。
この5つの条件をすべてクリアして、初めて「適法な引用」と認められます。一つでも欠けてしまうと、無断転載とみなされ、著作権侵害になってしまう可能性があるので、十分に注意しましょう。
【シーン別】広報活動で判断に迷う著作権Q&A
理屈は分かっていても、実際の業務では「これってどうなの?」と判断に迷う場面が出てくるものです。ここでは、広報の現場でよくある3つのシーンをQ&A形式で解説します。
Q1. Webで見つけた素敵な写真を、自社のブログ記事で使いたい。どうすればいい?
A1. 絶対に無断で使用してはいけません。必ず利用許諾を確認しましょう。
検索エンジンで見つけた個人や企業のブログ、ニュースサイトの写真を、安易にダウンロードして自社のコンテンツに使うのは最も典型的な著作権侵害です。写真には必ず撮影者(またはその所属組織)の著作権があります。
【安全な対処法】
- フリー素材サイトを利用する:著作権フリーや、定められたライセンスの範囲内で無料利用できる写真を提供しているサイトを活用しましょう。
- 有料のストックフォトサービスを利用する:高品質な写真を安心して使いたい場合は、有料の写真素材サービスと契約するのが確実です。
- 自分で撮影・作成する:最も安全なのは、自社で写真やイラストを用意することです。オリジナル写真であれば著作権は自社に帰属しますが、被写体に写っているもの(人物、建築・施設、商標・ブランド)への権利には注意が必要です。
(注意)
プレスリリースなどでメディアに素材を提供する際は、特に注意が必要です。自社で購入した写真やイラスト、Webサイトからダウンロードしたフリー素材などをそのまま挿入や添付した場合、メディアがそれらの素材を記事に転載できないケースがほとんどです。
その理由は、素材の利用規約に「第三者への譲渡禁止」や「転載禁止」が明記されていることが多いためです。メディアが記事に使用することは、この規約に抵触する可能性があります。
素材画像に文字を乗せたり、簡単な合成したりするなど、プレスリリースのコンテンツと一体化させるような加工を施すことで、当該コンテンツの用途でのみ利用が認められる場合もあります。しかし、判断に迷う場合は、必ず事前に利用規約を確認し、不明な点があれば素材提供元に問い合わせるようにしましょう。
Q2. 他社の興味深い調査リリース。自社のSNSで紹介するときの注意点は?
A2. 「公式のシェア機能」を使うのが基本。コピペはNGです。
X(旧Twitter)の「リポスト(リツイート)」やFacebookの「シェア」機能、Webサイトの埋め込み機能など、プラットフォームが公式に用意している機能を使って情報を拡散するのは、元の著作権者に通知がいく仕組みになっているため、一般的に問題ありません。
【注意すべき点】
- 文章や画像のコピペはNG:他社の投稿文や調査結果のグラフ画像をスクリーンショットし、自分の投稿としてテキストや画像を貼り付けて発信するのは、無断転載にあたります。
- コメントを添える場合:公式シェア機能を使って紹介する際に、自社の意見や感想を添えるのはOKです。このとき、自分のコメントが「主」、シェアした情報が「従」という主従関係を意識すると、より丁寧な発信になります。
Q3. メディアに掲載された自社記事。実績として公式サイトに載せても大丈夫?
A3. 原則として、掲載したメディアの許可が必要です。
自社について好意的に書かれた記事は、ぜひとも多くの人に見てもらいたいですよね。しかし、新聞や雑誌、Webメディアに掲載された記事の著作権は、多くの場合、執筆した記者や、そのメディアを運営する新聞社・出版社にあります。
【正しい手順】
- メディアの担当者に連絡:記事を二次利用(自社サイトへの掲載など)したい旨を伝え、許諾を得ます。
- 利用条件を確認:掲載にあたってのルール(「〇〇新聞社提供」といったクレジット表記の義務、利用料の有無など)を必ず確認し、遵守します。
- リンクで紹介する:もし許諾が得られない場合は、記事の全文を転載するのではなく、公式サイトで「〇〇に掲載されました」と報告し、元記事へのリンクを貼る形であれば問題ありません。
「自社のことだから」という思い込みは禁物です。メディアとの良好な関係を維持するためにも、必ず筋を通すようにしましょう。
著作権侵害がもたらす3つの企業リスク
特にリソースの限られるスタートアップや中小企業にとって、うっかり著作権を侵害してしまったら、そのダメージは計り知れません。ここでは、著作権侵害がもたらす具体的な3つのリスクについて解説します。
リスク①:損害賠償や使用差し止め請求(金銭的・事業的リスク)
著作権を侵害された権利者は、侵害した者に対して、コンテンツの使用差し止めや、侵害によって生じた損害の賠償を請求する権利があります。
- 損害賠償:侵害がなければ得られたはずのライセンス料や、侵害者が得た利益などが損害額として算定されます。
- 差し止め:侵害しているコンテンツ(ブログ記事、SNS投稿、パンフレットなど)をすべて削除・回収しなければならず、それまでにかけてきた労力やコストが無駄になってしまいます。
リスク②:企業イメージやブランド価値の低下(レピュテーションリスク)
著作権侵害が発覚し、それがSNSやメディアで報じられた場合、企業の評判は大きく傷つきます。「他人の権利を軽視する会社」「コンプライアンス意識が低い会社」といったネガティブなレッテルが貼られてしまうのです。
一度失墜したブランドイメージを回復するのは、非常に困難です。特に、誠実さが求められるBtoB企業や、クリエイターとの共存が重要な業界では、致命的なダメージになりかねません。
リスク③:メディアや社会からの信頼失墜(リレーションシップリスク)
広報担当者にとって、メディアやインフルエンサー、そして生活者との信頼関係は何よりの財産です。著作権侵害という不誠実な行為は、この大切な信頼関係を根底から揺るがします。
「あの会社は、メディアの記事を無断で転載していた」 「クリエイターの権利を守らない企業だ」
このような噂が広まれば、今後の取材協力が得られにくくなったり、SNSでのエンゲージメントが低下したりと、広報活動そのものが立ち行かなくなる可能性すらあります。
たった一度の「知らなかった」「これくらい大丈夫だろう」が、事業の継続を脅かすほどの大きな代償につながるのです。
明日から使える著作権侵害防止チェックリスト
日々の業務の中で、著作権侵害を100%防ぐためには、発信する前の「最終確認」を習慣化することが何よりも重要です。ここでは、ひとり広報担当者の方でも無理なく実践できる、シンプルなセルフチェックリストをご紹介します。
コンテンツを公開するボタンを押す前に、少しだけ立ち止まって、以下の5つの項目を確認してみてください。
【広報担当者のための著作権セルフチェックリスト】
☐ 1. このコンテンツの「権利者」は誰か、明確ですか?
- 文章、写真、イラスト…それぞれの著作権は誰にある?
- 自分で作成・撮影したものか? 社内のデザイナーが作成したものか?
- 外部から調達したもの(フリー素材、購入素材、提供素材)か?
☐ 2. 他者の著作物を使う場合、「引用の5条件」を満たしていますか?
- 引用する必要性はあるか?(必然性)
- カギ括弧などで区別されているか?(明瞭区別性)
- 自分の文章がメインになっているか?(主従関係)
- 出典(サイト名、URLなど)は正しく記載したか?(出所の明示)
- 元の内容を勝手に変えていないか?(改変しない)
☐ 3. フリー素材の場合、「利用規約」を最後まで読みましたか?
- 商用利用は許可されているか?
- クレジット表記は必要か?不要か?
- 加工や改変はどこまで許されているか?
- 禁止事項(例:商品化して販売する、公序良俗に反する利用など)に触れていないか?
☐ 4. 許諾が必要な場合、正式な「許可」を得ていますか?
- メディア掲載記事の二次利用許諾は取ったか?
- インタビュー相手の写真掲載の許可は得ているか?
- 取引先から提供されたロゴや写真の利用範囲は確認したか?
- 口約束ではなく、メールなど記録に残る形で許諾を得ることが望ましい。
☐ 5. 全体を通して、他者の創造物への「リスペクト」がありますか?
- この発信は、元の著作者を不快にさせないか?
- 元の著作物の価値を不当に貶めるような使い方をしていないか?
このチェックリストをチームで共有するのもお勧めです。一つひとつの確認作業が、あなたと会社を未来のトラブルから守る盾となります
著作権フリー素材とライセンスの賢い使い方
著作権のルールは、何かを「禁止する」ためだけにあるのではありません。ルールを正しく理解すれば、世界中のクリエイターが公開している素晴らしい素材を、安心して自社の広報活動に活用することができます。
ここでは、リスクを回避する「守り」の知識から一歩進んで、コンテンツの質を高める「攻め」の知識として、著作権フリー素材とライセンスの賢い使い方をご紹介します。
「著作権フリー」=「何をしてもOK」ではありません。
よく「著作権フリー」という言葉を耳にしますが、これは少し注意が必要な言葉です。「著作権が放棄されている(パブリックドメイン)」という稀なケースもありますが、多くの場合「定められた利用規約(ライセンス)の範囲内であれば、無料で自由に使っていいですよ」という意味で使われています。
サイトによって規約は様々ですので、「フリー素材だから」と油断せず、必ず各サイトの利用規約に目を通す習慣をつけましょう。特に「商用利用の可否」と「クレジット表記の要不要」は最重要チェックポイントです。
まとめ
著作権の知識を身につけることは、単に「炎上を避ける」「法律違反をしない」といったリスク回避のためだけではありません。
他者が時間と情熱をかけて創り出した創造物へ敬意を払う姿勢は、企業の誠実さの表れであり、社会からの信頼を醸成する土台となります。それは、広報担当者が最も大切にすべき「信頼関係の構築」そのものと言えるでしょう。
正しい著作権の知識は、あなたと会社を不測のトラブルから守る「盾」であると同時に、より質の高い情報発信を可能にする「武器」でもあります。
無理なく、安全に、そして効果的に広報活動を進めるための基礎知識として、ぜひ日々の実務に活用してください!