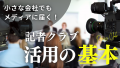スタートアップや中小企業で広報を担っている皆さん、「テレビに取り上げてもらいたいけど、何から始めればいいかわからない」と感じたことはありませんか?限られたリソースの中で、どうアプローチすればメディアに注目され、実際にテレビ番組で取り上げてもらえるのか。この記事では、テレビPRの基本から、番組に合った企画の立て方、アプローチの仕方までを解説します。
そもそもテレビPRとは?CMとの決定的な違い
まず基本として、テレビPRとは、自社の製品、サービス、企業活動などを、テレビ番組内でニュースや情報として紹介してもらうことを目的とした広報活動(Public Relations)です。
多くの人が混同しがちな「広告(CM)」とは、性質が全く異なります。
| 項目 | テレビPR(パブリシティ) | テレビCM(広告) |
|---|---|---|
| 費用 | 原則無料 | 有料(高額) |
| 情報の発信者 | テレビ局(第三者) | 企業(当事者) |
| 情報の見え方 | ニュース、客観的な紹介 | 宣伝、広告 |
| 視聴者の信頼度 | 高い | 比較的低い |
| 内容のコントロール | 不可(編集権はテレビ局) | 可能(企業が自由に制作) |
CMは莫大な費用がかかる一方、PRは原則無料です。そして何より、番組という「第三者」の視点から報道・紹介されるため、「パブリシティ(Publicity)」としての価値が生まれます。視聴者は「テレビ局がわざわざ取材しているのだから、信頼できる情報だ」と感じ、情報が非常にポジティブに受け入れられます。この「信頼性の高さ」こそ、テレビPRが持つ最大の強みです。
さらに、テレビPRは採用活動への好影響、社員のモチベーションアップ、取引先からの信頼向上、他のメディアからの二次取材など、ビジネス全体に好循環を生むポテンシャルを秘めています。広告予算の限られる中小企業にとって、極めて費用対効果の高い戦略なのです。
なぜ今、テレビなのか?絶大なリーチ力と揺るぎない信頼性
「もうテレビの時代は終わり」という声もありますが、データを見ると、テレビが依然として強力なメディアであることがわかります。
① 抜群のリーチ力
総務省の「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によると、テレビ(リアルタイム)視聴は、全年代で平日・休日ともに20時台が高く、平均視聴時間は平日でも1日2時間半を超えています(※1)。さらに、NHK放送文化研究所の調査によれば、テレビ(リアルタイム)番組を1週間に1度以上視聴する人の割合は、全世代平均で83%にも上ります(※2)。
これは、特定のターゲットに深くリーチするWeb広告とは異なる「マスリーチ」です。老若男女問わず、非常に幅広い層に一斉に情報を届ける力を持っています。仮に関東地区で視聴率10%の番組で取り上げられれば、単純計算で約400万人が同時にその放送を見ることになります。この規模のリーチは、他のメディアではほぼ不可能です。特に、知名度の低いスタートアップや中小企業にとって、自社の存在を一気に世に知らしめる絶好の機会となります。
※1 総務省情報通信政策研究所「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 https://www.soumu.go.jp/main_content/001017159.pdf
※2 NHK放送文化研究所「メディア選択 “選び取る”時代に~「全国メディア意識世論調査・2024」の結果から~」https://www.nhk.or.jp/bunken/d/_data/research/yoron/BUNA0000010750080002/files/20250801_01.pdf
② 信頼性の高さ
テレビは今もなお、「信頼できる情報源」として広く認識されています。総務省の調査では、「世の中のできごとや動きについて信頼できる情報を得るために最も利用するメディア」は、「テレビ」が全体の51.6%と最多で、新聞やインターネットを上回っています(※1)。
この背景には、放送法に基づく公平性の確保や、放送前に行われる厳正な内容チェック(考査)の存在があります。こうした制度によって「テレビで放送される情報は信頼できる」という社会的な共通認識が形成されており、そのことがテレビというメディア全体の信頼性を支えています。
その結果、テレビで紹介された情報や商品・サービスは、視聴者から「安心できる」「信頼できる」と受け取られやすくなります。実際に、「テレビで紹介されていたから買ってみた」「家族が番組で見て話題にしていた」といった口コミが生まれやすく、他のメディアよりも早く・広く・深く認知が浸透していく傾向があります。
特に、シニア層やファミリー層といったテレビ視聴の習慣が根強い層に向けた商品・サービスでは、こうした「信頼性」と「リーチ力」の掛け合わせによって、大きな反響を得る可能性が高まります。問い合わせや購買など、実際の行動につながるケースも少なくありません。
テレビマンの思考を覗く!番組に「選ばれる」3つの共通ポイント
では、どうすればテレビ番組に選ばれるのでしょうか。そのためには、番組制作者(ディレクターやプロデューサー)の視点を理解することが不可欠です。彼らは毎週の企画会議で「今、視聴者が求める面白いネタは何か?」を探しています。
実際に採用される企画には、ある程度の共通点や傾向があります。ここでは特に意識したい3つのポイントをご紹介します。
ポイント1:時事性・社会性(なぜ「今」なのか?)
テレビは「今」を映すメディアです。「なぜ今この情報を取り上げるのか?」という明確な理由がなければ、企画としては弱くなってしまいます。
- 季節性: 猛暑、クリスマスなど、季節のイベントや気候に関連づける。「猛暑を乗り切る最新ひんやりグッズ」などは定番
- 社会的トレンド: SDGs、働き方改革、Z世代の価値観など、社会的な関心事と自社の取り組みを結びつける。「食品ロス削減に貢献するユニークな自販機」など
- ニュースとの連動: インバウンド回復、政府の新政策など、時事ネタとのタイミングを活かす
自社の魅力を「今、この社会背景があるからこそ意味がある」と伝えることが、テレビマンの心を動かす第一歩です。
ポイント2:視聴者メリット・共感性(「自分ごと」になるか?)
番組は視聴者のために作られています。あなたの会社やサービスが、視聴者の生活にどんなメリットをもたらすのか、「自分ごと」として捉えてもらう視点が重要です。
- 悩み解決: 「なるほど!」「便利!」と感じられる情報(例:頑固な汚れが簡単に落ちる洗剤)
- お得・時短: 「知らなきゃ損!」と思わせる金銭的・時間的メリット(例:10分でできるプロの味レシピ)
- 新しい体験・知識: 「へぇ〜!」と知的好奇心をくすぐる情報(例:話題のスポット、新しいレジャー)
「私たちのサービスは、視聴者の〇〇という悩みを解決できます」というベネフィットを明確に打ち出しましょう。
ポイント3:映像的魅力・ストーリー性(「画」になり、心を動かすか?)
テレビは映像メディアです。企画書を見た番組制作者が「面白そうな映像が撮れそうだ」と具体的にイメージできるかがカギです。
- 動きや変化: 製造工程のダイナミックな動き、ビフォーアフターの劇的な変化など、映像的な面白さがあるか
- ビジュアルの魅力: カラフルな商品、シズル感のある料理など、思わず見入ってしまう画力
- 面白い「人」と「物語」: ユニークな経歴の社長、開発の苦労話、社会課題への挑戦など。視聴者の感情に響くストーリーがあると、番組に取り上げられる可能性が一気に高まります。
あなたの会社に眠るストーリーを掘り起こし、テレビ映えする魅力として打ち出すことで、メディア掲載の可能性を飛躍的に高めることができます。
成功は準備で決まる!戦略的番組リサーチの進め方
やみくもなアプローチは無駄撃ちに終わります。緻密な「番組リサーチ」で、自社のネタをどの番組に届けるべきかを見極めましょう。
Step1:ターゲット番組のリストアップ
まずは、自社の商品やサービス、事業内容と親和性の高そうな番組をリストアップすることから始めましょう。テレビ番組は、大きく以下のように分類できます。
- 報道番組(朝・夕・夜): ニュース性が高く、社会問題や経済トレンドを扱うコーナーが多い。時事性と社会性が特に重視される。
- 情報番組(朝・昼のワイドショー): 視聴者の生活に密着したテーマが中心。トレンド、グルメ、健康、お悩み解決などのネタが好まれる。
- バラエティ番組: エンターテインメント性が最優先。「面白い!」「すごい!」といった驚きや笑いが求められる。ユニークな特技や珍しい商品などがハマりやすい。
- 経済番組: 企業のビジネスモデルや戦略、経営者の人物像にフォーカスする。独自性や将来性が評価される。
- 地方局の番組: 地域密着がテーマ。地元の新店舗、地域貢献活動、地元企業の面白い取り組みなどが取り上げられやすい。
自社のネタがどのジャンルに最も適しているかを考え、候補となる番組名を洗い出します。
Step2:徹底的な番組分析
リストアップした番組を、今度は一つひとつ徹底的に分析します。可能であれば、1週間分ほど録画して視聴するのが理想です。「TVer」などの見逃し配信サービスを活用するのも良いでしょう。
以下のチェックリストを参考に、番組を解剖してみてください。
【番組分析チェックリスト】
- □ 番組の基本情報:
- 放送局、番組名、放送曜日・時間帯
- メインキャスター、司会者、コメンテーターの顔ぶれと発言の傾向
- □ 全体のコンセプトとトーン:
- 番組全体の雰囲気は?(硬派、軟派、アットホーム、スタイリッシュなど)
- 主な視聴者層は誰か?(年齢、性別、ライフスタイルを推測)
- □ コーナーの構成:
- どんなコーナーがあるか?(ニュース、特集、トレンド、グルメ、中継など)
- 各コーナーの時間はどれくらいか?(2〜3分の短いものか、10分以上の特集か)
- 自社のネタは、どのコーナーにハマりそうか?
- □ 過去の放送内容の分析:
- 過去にどんな企業や商品が取り上げられたか?(特に自社と類似するテーマ)
- どのような切り口(ストーリー)で紹介されていたか?
- どんな映像(VTR)構成だったか?(インタビュー、再現VTR、スタジオでの実演など)
- BGMやテロップの使い方はどんな感じか?
この分析を通じて、「この番組は中小企業の挑戦ストーリーが好きだな」「このコーナーは主婦向けの時短グッズをよく取り上げている」「この番組は社長のキャラを立てる演出が多いな」といった、各番組の「クセ」や「好み」が見えてきます。
Step3:アプローチ先の優先順位付け
分析が終わったら、自社のネタとの親和性が最も高く、採用される可能性が高いと思われる番組から順に、アプローチリストを作成します。すべての番組に同じ企画書を送るのではなく、分析結果に基づいて「A番組には、このコーナー向けに、この切り口で提案しよう」「B番組には、社長のキャラクターを前面に出してアプローチしよう」と、番組ごとに企画書を作ると良いでしょう。
「映像が浮かぶ」PR企画書の作り方
テレビ局向けの企画書は、「読んだ番組制作者の頭の中に、放送シーンの映像が浮かぶか」が全てです。A4用紙2枚程度に、以下の要素を視覚的にまとめましょう。
- 企画タイトル: 番組のコーナー名になってもおかしくない、キャッチーで内容が一目でわかるものに。「〇〇のご案内」はNGです。
- 企画概要: 冒頭の数行で企画の核心(5W1H)を伝えます。ディレクターはここで続きを読むかを判断します。
- 社会背景・文脈: なぜ「今」このネタが面白いのかを、トレンドやデータを用いて論理的に説明します。
- 【最重要】具体的な撮影可能シーン: 「こんな画が撮れます」という提案を箇条書きで具体的にリストアップします。(例:代表へのインタビュー、製品の製造工程、お客様の喜びの声、スタジオでの実演など)
- 写真・ビジュアル資料: 人物、製品、現場の様子など、魅力が伝わる写真を複数挿入し、映像のイメージを助けます。
- 連絡先: 担当者名、電話番号、メールアドレスを分かりやすく記載します。
「文字だらけ」「専門用語が多い」といった企画書は、読まれることなくゴミ箱行きです。相手(番組制作者)を想い、熱意と工夫を込めて作成しましょう。
企画書を届ける!番組制作者へのアプローチ
企画書が完成したら、いよいよ「届ける」フェーズです。
方法1:番組サイトの情報提供窓口
多くのテレビ番組の公式サイトには、「情報提供はこちら」「取材依頼はこちら」といった専用の連絡窓口が設けられています。まずはそこへ、簡潔に企画内容をまとめたメールを送るのが王道のアプローチです。メールの件名を「【情報提供】株式会社〇〇/(キャッチーな企画タイトル)」のように工夫し、本文は簡潔に、企画書をPDFで添付して送りましょう。
方法2:記者クラブへの投げ込み
特に地方局やローカル番組を狙う場合は、「記者クラブ」を活用する方法もあります。記者クラブには、番組スタッフや新聞記者など、地元メディア関係者が出入りしており、プレスリリースや企画資料が共有される場になっています。テレビ局に直接のつながりがないスタートアップや中小企業でも、広く情報を届ける手段として有効です。
▼あわせて読みたい
小さな会社でもメディアに届く!記者クラブ活用の基本
方法3:SNSでのダイレクトアプローチ
番組ディレクターやプロデューサーの名前がわかった場合、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSでダイレクトメッセージ(DM)を送るという方法もあります。ただし、この場合はビジネスマナーを守り、いきなり長文を送らず、まずは簡潔に「情報提供のご相談が可能でしょうか」といったスタンスで接触するのがベターです。
提案文の工夫で、“刺さる”一歩を
情報提供時には、以下のような「番組スタッフがイメージしやすい工夫」をすると、取材採用率が上がります。
例:「昨年、貴番組で〇〇が特集されていましたが、当社の取り組みも同様の社会課題に向き合っており、新たな視点をご提供できると考えています。」
こうした言い回しを加えることで、番組スタッフは過去の構成や演出の文脈を想起しながら、新たな切り口として検討しやすくなります。「自社の魅力を伝える」のではなく、「番組のストーリーとして成立するかどうか」の視点を持つことが、テレビPR成功へのカギとなります。
まとめ
テレビPRは、番組の特性を理解し、視聴者に届くストーリーを描き、それを番組制作者に「放送したい」と思わせる仕掛けが求められます。
準備やリサーチ、丁寧なアプローチまで、一つひとつの積み重ねが成功に繋がるのです。
広報初心者でも、今回ご紹介した基本ステップを押さえることで、十分にテレビ取材のチャンスを掴むことができます。ぜひ地道に情報を集め、あなたの企業の魅力を、次はテレビの視聴者に届けてみてください!