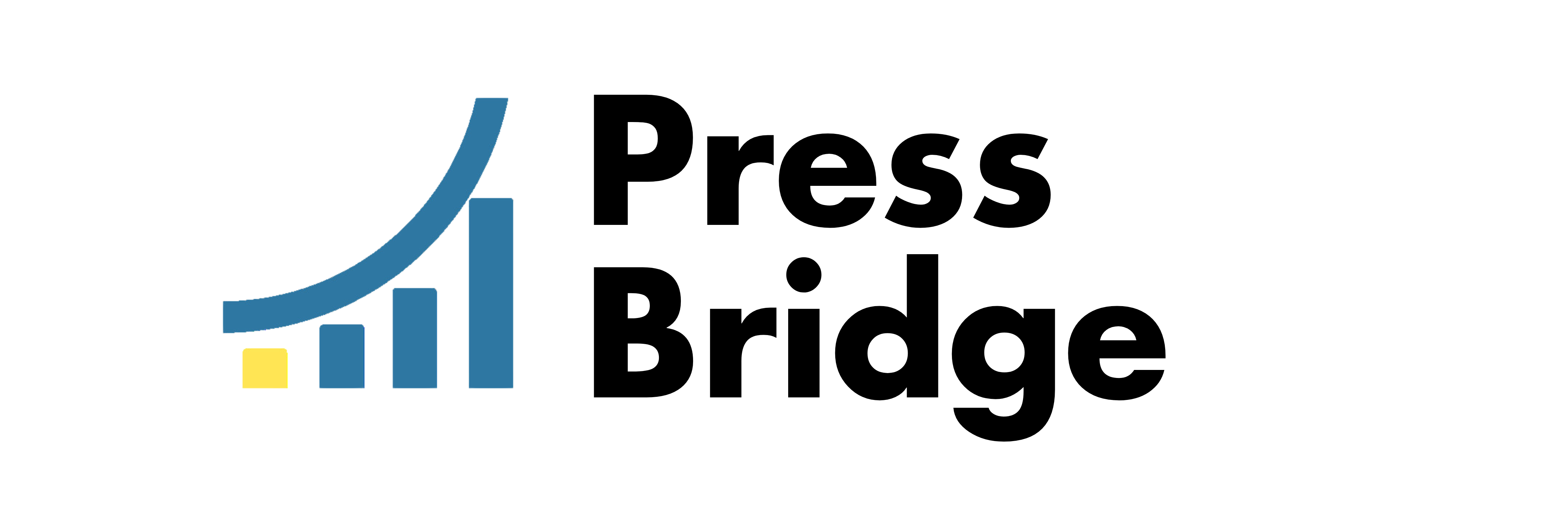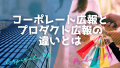広報担当として働き始めたばかりの方の多くが、最初にぶつかる壁のひとつが「ネタがない」という悩みではないでしょうか。実は社内には、広報向きの“使えるネタ”がたくさん眠っています。でもそれを見つけ出すには、広報部門だけでなく他部署の協力が欠かせません。
この記事では、他部署と上手に連携して社内ネタを見つけるためのヒントをご紹介します。広報初心者の方でもすぐに実践できる内容にしていますので、ぜひ参考にしてください。
まずは「社内にどんなネタがあるか」を知る
社内ネタと聞いても、最初は何が“ネタ”になるのか分からないものです。実は、広報の目線で見れば、日常の業務やちょっとした取り組みも立派な情報資産になります。
例えば、以下のようなことも立派なネタです。
- 営業部が地域イベントに協賛した
- 開発部で新しい製品の試作品を作った
- 総務部が社内のDX化を進めている
- 若手社員が業務改善の提案をして採用された
一見、社内では「当たり前」と思われていることでも、外部の人から見ると新鮮で価値ある情報になることはよくあります。まずは「何がネタになり得るか」という視点を持ち、社内の動きを“広報的に”見ていくことがスタートです。
ここでいう“広報的に見る”とは、「この出来事を社外に伝えたとき、どんな人が興味を持ち、どう企業イメージにつながるか」を意識することです。例えば、単なる業務報告ではなく「会社の姿勢が伝わる」「社員の人柄が見える」「お客様の信頼につながる」といった切り口で捉えていく姿勢が重要です。
他部署は「広報のこと」をよく知らないと心得る
ネタを見つけるには、他部署の協力が欠かせません。しかし、いざ「何か情報をください」と声をかけても、「これは広報向きじゃないよね?」と返されてしまうこともあります。これは非協力的なのではなく、そもそも広報の目的や価値を知らないだけ、というケースが大半です。
広報の役割や視点を丁寧に伝えることが、協力を得る第一歩です。例えば、「広報は社内の活動を社外にわかりやすく伝える役割があり、どんな取り組みでも“人が動いていること”があれば記事になります」と説明すれば、他部署の方にもイメージが湧きやすくなります。
さらに「その情報が企業のブランドづくりや信頼の構築につながる」という視点も補足すると、広報の意義がより明確になります。よく「社内の既知は社外の未知」と言われるように、社内で当たり前と思われていることでも、視点を変えることで大きな価値が生まれるのです。
例えば、日常の業務を社会的なトピック(世の中ゴト)と関連づけたり、メディアの関心と重ね合わせたりすることで、“今伝えるべき意味”を持たせることができます。こうして社内の情報に編集を加え、社外に届けることで、企業の姿勢や魅力が伝わり、結果としてブランドや信頼の向上につながる——これが“広報的に見る”ということなのです。
他部署との信頼関係をつくるコツ
他部署からネタをもらうためには、何よりも「信頼関係」が大事です。とはいえ、いきなり「いいネタください」と言っても、ハードルが高いもの。まずは気軽なコミュニケーションから始めてみましょう。
例えば:
- 雑談の中で「最近何か面白いことありましたか?」と尋ねる
- 朝礼や社内報で見かけたトピックに反応して声をかける
- 社内チャットで「広報で取り上げたい事例を探しています」と投げかける
最初は「話すだけ」「聞くだけ」で十分です。相手が「この人なら気軽に話せる」と思ってくれると、情報の提供につながりやすくなります。
また、他部署からもらったネタを、しっかり記事や投稿として形にし、その結果(例えば社外からの反響など)を本人やチームにフィードバックするのもポイントです。「ちゃんと発信してくれてるんだ」と信頼が生まれ、次の協力にもつながります。
ネタ集めを仕組みにする方法
他部署との信頼関係を築いたら、次は“ネタ集めを仕組みにする”ことを考えてみましょう。一度きりのヒアリングではなく、継続的に情報を得られるようにすることで、広報活動がぐんとスムーズになります。
以下のような仕組みが効果的です:
- 毎月、部署ごとに「今月のトピック」を提出してもらう(Googleフォームなどで簡単に)
- 月1回、全社の情報共有会議に参加して、広報視点の質問をする
- 社内チャットに「ネタ共有チャンネル」をつくり、自由に書き込んでもらう
- 社内報やイントラで「この部署のこんな取り組み、紹介しました」と実例を紹介し続ける
情報提供する側の「面倒」「よく分からない」というハードルを下げる工夫が大切です。「一言でもいいので教えてください」と声をかけるなど、参加しやすい空気づくりを意識してみましょう。
最終的には「自分で歩くアンテナ」に
他部署との協力が得られてくると、だんだん「今度この話、広報さんに伝えたらいいかな」と自発的に声をかけてもらえるようになります。ここまで来れば大きな前進です。
でも実は、最も強いのは、広報自身が「歩くアンテナ」になることです。日常的に社内の動きに興味を持ち、雑談や観察から情報を拾っていくこと。現場の会話や社内の掲示板、社員のSNS投稿など、あらゆるところに“ネタの種”は転がっています。
例えば、製造現場に足を運び「この機械、いつ導入されたんですか?」と聞いてみたり、イベントの設営に同行して「誰が企画したんですか?」と尋ねるだけでも、思わぬストーリーに出会えたりします。
大切なのは、社内の人や出来事に関心を持ち続けること。その姿勢こそが、信頼もネタも集まる源になります。
まとめ
広報初心者にとって、他部署からネタをもらうことはとても大きなハードルのように感じるかもしれません。でも、少しずつ関係性を築き、目的や意義を共有することで、協力を得ることは十分に可能です。
まずは「どんなことがネタになるか」を自分の中で整理すること。次に、「広報が何をしているか」を丁寧に説明しながら、他部署との信頼関係を育てましょう。そして、仕組みづくりと自分の行動力を掛け合わせて、社内に眠っている“原石”を発見していってください。
広報の仕事は「社内の魅力を見つけて、社外に伝える」ことです。その第一歩は、社内への関心と、仲間への感謝から始まります。信頼関係を育て、情報をつなぎ、会社の“今”を広く伝えていきましょう!